CO2濃度の変動は気温変動に遅れている(ラグがある)
科学的知見...
地球の氷河期が終わる際、温暖化はCO2ではなく地球の軌道要素の変化によって開始される。温暖化によって海洋はCO2を放出し、大気と混合し、地球上の温暖化を増幅させる。つまりCO2は温暖化の原因でもありながら、温暖化の結果でもあります。
「Scienceに掲載されてる記事では、気温の上昇がCO2濃度の変動を(200〜1000年)先行しているとある。CO2濃度が気温を追っていたのならば、近年の人為的温暖化説はデータを矛盾している。」(Joe Barton)
過去50万年、地球の気候は長い氷河期の間に比較的短期な温暖化期間(間氷期)を経験してきました。大気中の二酸化炭素濃度は、氷河期の周期と一致した形で気温上昇とともに80~100ppm上昇しています。歴史記録を注意深くみれば、CO2が気温を1000年あたりラグしてる。この結果は20年前から分かっていた事ですが(Lorius 1990)、今でも混乱を招きます。温暖化はCO2増加を示唆するのか、それとも逆の因果関係なのか?答えは両方です。

図1:ボストークの氷コア記録からCO2濃度データ(Petit 2000)と気温変動(Barnola 2003)。
間氷期は大体10万年周期訪れる。これはミランコビッチサイクルと呼ばれており、地球の軌道変化に起因されます。地球の軌道変化には主に三つあります。軌道の形状を指定する要素として、地球の公転軌道の離心率(eccentricity)は楕円形から円形まで変形する。自転軸の傾きは太陽と比較して23°あたり。この自転軸の傾斜角(obliquity)は22.5°~24.5°の間を振動する。地球が軸を回転していると、歳差運動(precession)が起き、軸の向きは北極星から織女星の間にぐらぐらする。

図2:軌道変化は主に三つの要因がある。地球の公転軌道の離心率(eccentricity)と自転軸の傾きの周期的変化(obliquity)、さらに自転軸の歳差運動(precession)。
この三つの要因により、長期的に地球にかかる日射量が変動する、高緯度地域では得に。例を挙げると、1.8万年前、南半球に当たる日射量が春季に上昇した。それによって南極の海氷は後退し、南半球の氷河が融解しだした(Shemesh 2002)。氷の減少によって正のフィードバック効果が生じ、氷からのアルベド効果をも減少しました。これは温暖化を加速しました。
南極海が温まると、CO2の水への溶解度は低下します(Martin 2005)。海洋はそれによってCO2を大気へと放出する。深海がどうCO2を放出するか正確なメカニズムはまだ分かっていないが、海洋における鉛直混合と考えられる(Toggweiler 1999)。このプロセスは800~1000年かかり、CO2濃度は1000年あたりの周期で上昇していると観測されてる(Monnin 2001, Mudelsee 2001)。
海洋からのCO2ガス放出はいくつかの効果があります。大気中のCO2上昇は本来の温暖化を増幅させます。比較的弱いミランコビッチサイクルからの強制力では、最近の氷河期を終了させた劇的な気温変動を説明するためには不十分です。しかし、CO2の増幅効果は観測した温暖化と一貫してます。
南極海からのCO2は大気とも混合し、北の気候をも温暖化させます(Cuffey 2001)。熱帯海洋堆積物からの記録では熱帯地方の温暖化が南極温暖化と同じ時期におきてる事が分かってます、CO2上昇と同じ時期です(Stott 2007)。グリーンランドの氷コアによれば、北半球の温暖化は南極CO2上昇をラグしています(Caillon 2003)。
CO2が温暖化をラグしているのを人為的温暖化の反証として挙げるのは、ミランコビッチサイクルの理解不足をあらわにしてます。査読された研究を検討してみればいくつかの結論にいたります:
- 退氷期はCO2ではなく、軌道変化によるもの。
- CO2は温暖化を増幅させ、近年の温暖化は軌道変化では説明できない。
- CO2は地球全体に温暖化を広める。
この記事に関連する懐疑論
もっと読む
CO2のラグと増幅効果は1990年に既にClaude Loriusにより予測されている(The ice-core record: climate sensitivity and future greenhouse warming):
「CO2とCH4の変動は、氷河期 - 間氷期から来る気候変動に、地球軌道と共に重要な役割を果たしている。」
この論文では軌道変化は氷河期が周期的に訪れる原因の一つと書いてある。ちなみにこの論文は、氷コアからの良質のデータが集められる10年以上も前の分析。今ではCO2ラグを確証できる正確なデータを科学者達は所有している。
Climate 411が簡潔に温室効果の事を説明する。
あるコメ欄から発掘した皮肉な一言:「鶏は卵を生まない、なぜなら卵を生むところを観察されたからだ」
もっと観る
Translation by apeescape, . View original English version.































 Arguments
Arguments




































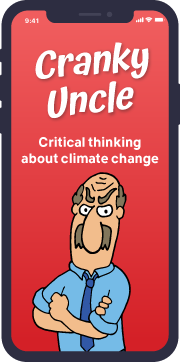





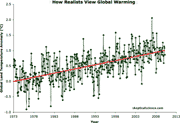
懐疑論...